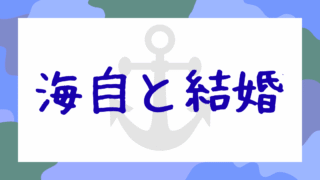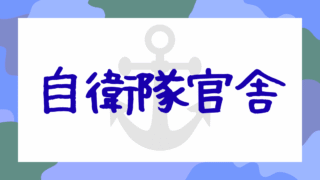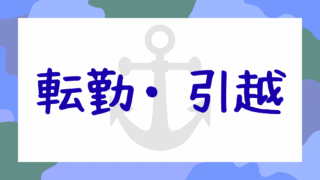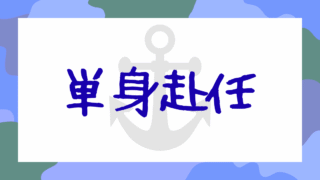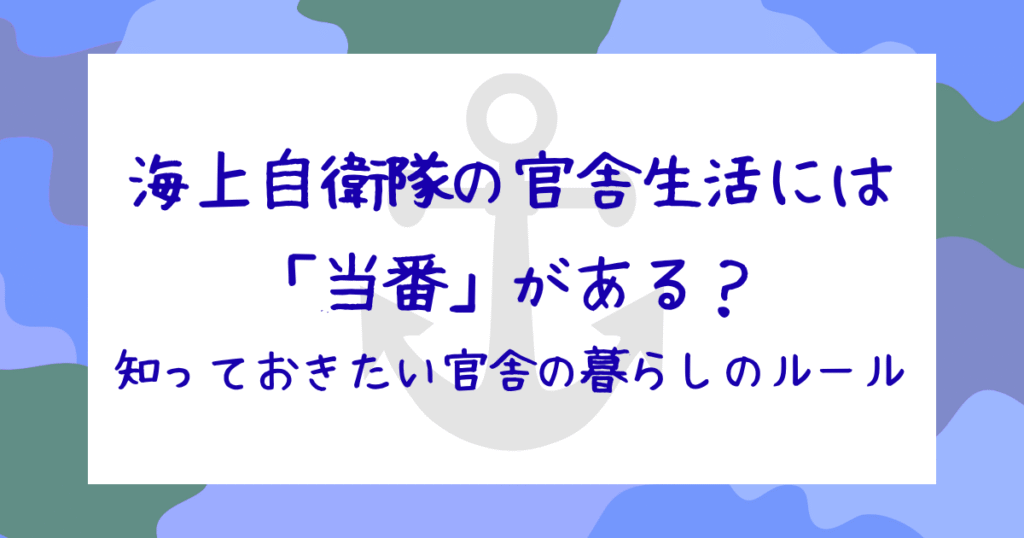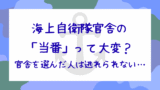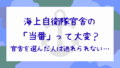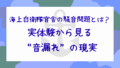自衛官のご家族として、これから官舎に住む予定の方、またはすでに住んでいる方へ。
民間の賃貸住宅とは少し違った“官舎ならでは”のルールとして、多くの官舎に存在するのが「当番制度」です。今回は、私が実際に体験した内容も交えながら、代表的な「月当番」と呼ばれるその仕組みについてご紹介します。
官舎生活のキホン:「当番」はほとんどの官舎で存在
海上自衛隊の官舎(自衛隊官舎)に入居すると、ほとんどのケースで「当番」があります。これは、住民全体で官舎の維持管理を行うための制度で、主に「月当番」と呼ばれる形で持ち回り制になっています。
「月当番」って何をするの?

「月当番」の具体的な内容は以下の通りです。官舎によって細かい違いはありますが、おおよそこのような業務が含まれます。
共用部分の掃除(階段・廊下・玄関など)
ゴミ置き場の管理(掃除や分別のチェック)
掲示物の更新(町内会のお知らせや注意喚起の掲示)
共益費や水道代の集金
回覧板の回付
どれも「ちょっとしたこと」ではあるのですが、住民みんなで分担しないと成り立たない、そんな地味に大切な役割です。
「自治会」のある官舎も
官舎によっては「自治会」が組織されていて、当番の名称や役割が多少異なることもあります。たとえば「清掃当番」「会役員」など、別の名称で区分されているケースも。
どちらにしても、“みんなで暮らしを支える”という考え方が根底にあります。
人数が少ないと……当番も早く回ってくる!?
小規模な官舎では、当然ながら当番が回ってくる頻度が高くなります。住民数が少ないぶん、一人ひとりの負担が重くなりがちです。
また、仕事や家庭の事情で「今月はちょっと難しい……」という場合もありますが、基本的に免除はなく、全員で協力して負担を分け合うのが原則です。
ただし、当番がない官舎も?
中には、自治会が存在しない官舎や、特別な事情で当番制度自体がない官舎もあります。
そのため、「この官舎には当番があるの?」「どんな内容なの?」という点については、入居前に必ず確認しておくのがおすすめです。
【まとめ】官舎は“助け合い”で成り立っている
官舎の当番制度は、最初はちょっと戸惑うかもしれません。でも、住民みんなで助け合いながら暮らしていく中で、自然と顔見知りが増えたり、困ったときに声を掛け合える関係が築けたりもします。
自衛隊の官舎は、ある意味で“ミニ共同体”のような場所。お互いに気持ちよく過ごせるよう、少しずつ協力しながらの生活が基本になります。これから官舎に入居される方の参考になれば嬉しいです!
↓次の記事では、代表的な月当番の他の当番についても詳しく説明します↓