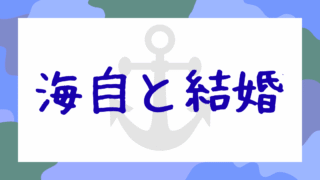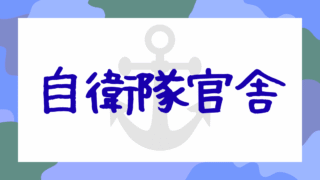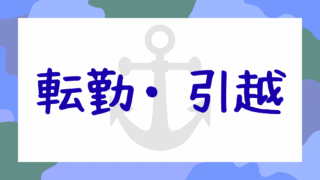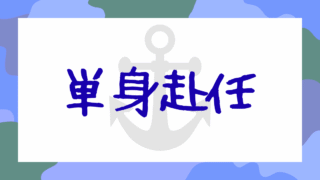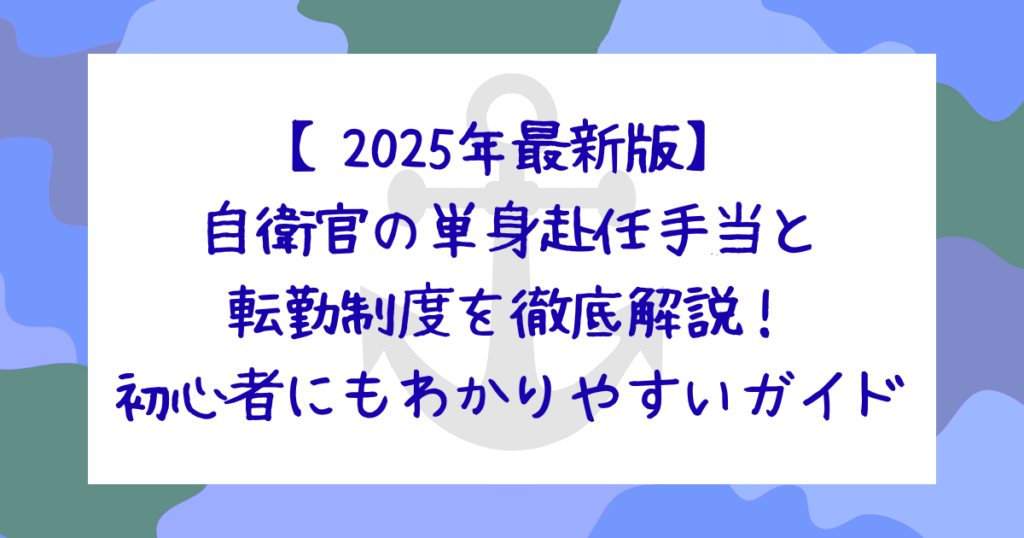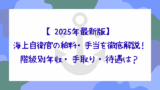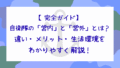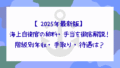自衛官として働く中で避けられないのが「転勤」と「単身赴任」です。突然の異動や、家族と離れて暮らすことになったときに「生活費はどうなるの?」「手当ってあるの?」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。
私自身、自衛官の単身赴任を身近に経験。その中で「転勤制度の仕組み」や「単身赴任手当の実際の金額・受け取り方」を知ることで、不安をぐっと減らすことができました。
このブログではそうしたリアルな経験をもとに、専門的な制度をできるだけやさしく解説していきます。この記事では、
- 自衛官の転勤の流れと勤務地の決まり方
- 単身赴任手当の条件や支給額の目安
- 住まい(営内・営外)の違いと生活の工夫
- 手当を受け取るための申請や注意点
などを、初心者にもわかりやすくまとめました。
この記事を読むことで、「転勤が決まったけど何から準備すればいいのか」「手当はどのくらいもらえるのか」といった疑問がクリアになり、安心して次のステップに進めるようになります。
自衛官にとって転勤や単身赴任は避けられない現実ですが、制度を正しく理解して活用すれば、家計や生活への負担を大きく減らせます。
この記事が、あなたの不安を少しでも軽くし、前向きに準備を始めるきっかけになれば幸いです。
海上自衛官の単身赴任手当以外の給料・手当が気になったらこちら▼
【2025年最新版】海上自衛官の給料・手当を徹底解説!階級別年収・手取り・待遇のリアルとは?
▼転勤が決まったけど、官舎には入らないつもりの人はアパマンショップでお部屋探し!
本ページはプロモーションが含まれています
自衛官の「転勤」と「単身赴任手当」は特殊な制度
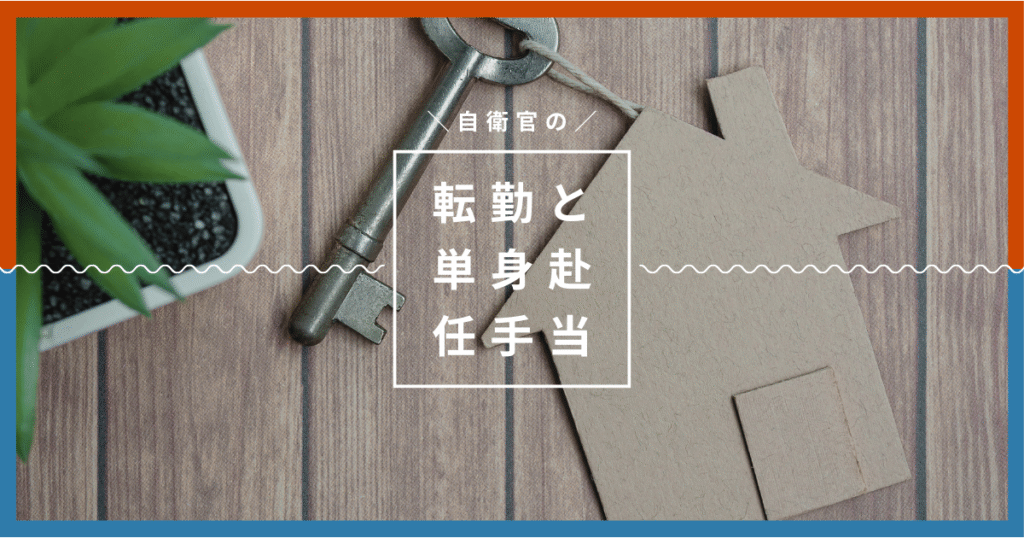
自衛官は全国転勤がある国家公務員であり、単身赴任になることも珍しくありません。その際に支給される「単身赴任手当」は、家族と離れて生活する自衛官を経済的に支える大切な制度です。
自衛隊は日本全国に部隊や基地があり、部隊の人員バランスや任務によって人事異動が定期的に行われます。特に幹部や特定の職種では数年ごとに転勤があるため、家族と離れて単身で暮らさざるを得ない場合があります。
例えば、北海道に配属された自衛官の方が、次に九州の部隊へ異動になる場合、家族が子どもの学校などの事情で一緒に引っ越せないと、単身赴任の対象となり、手当が支給される仕組みです。
この記事では、自衛官の転勤制度と単身赴任手当について、初心者にもわかりやすく、制度の仕組みや金額、注意点まで詳しく解説していきます。
第1章:自衛官の転勤制度の基礎知識
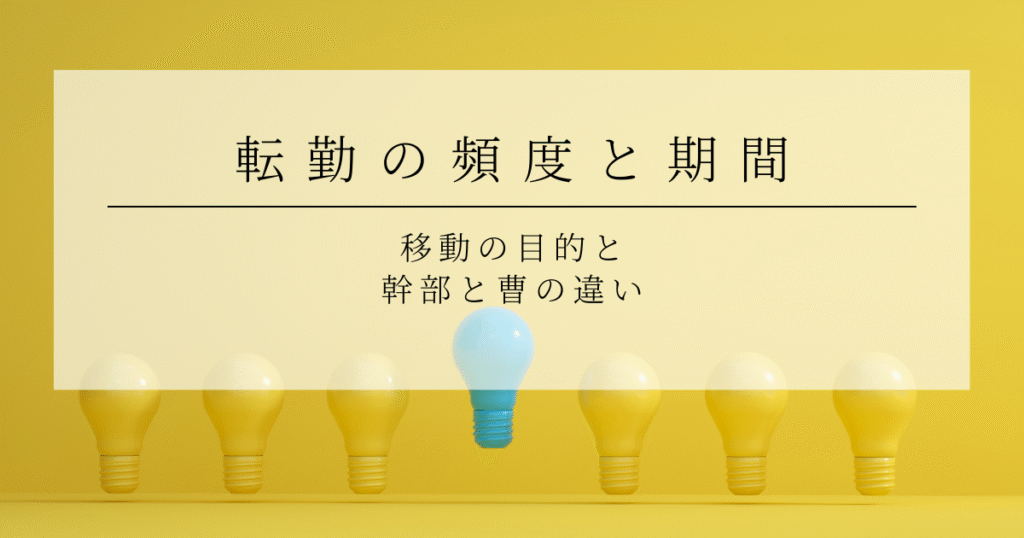
1-1. 転勤の頻度と期間
自衛官は、職種や階級によって転勤の頻度が異なります。幹部ほど転勤が多く、曹は比較的少なめです。
自衛官の異動は「任務遂行」と「人材育成」の目的があります。特に幹部は将来の指揮官候補として多くの経験を積む必要があるため、平均して2〜3年ごとに転勤が発生します。一方、曹(中堅の隊員)は長く同じ部隊に勤務するケースもあります。
幹部自衛官の場合、20年間の勤務のうち7〜10回の転勤があることも珍しくありません。反対に、曹の自衛官は10年で2〜3回程度という例もあります。
転勤の頻度はキャリアパスに応じて違いますが、「転勤=異常」ではなく、自衛隊にとっては通常業務の一環であることを理解しておくことが重要です。
| 階級 | 転勤の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 幹部(例:2佐、3佐) | 約2~3年ごと | 全国転勤が前提 |
| 曹(例:1曹、2曹) | 約5~10年ごと | 比較的少なめ |
1-2. 転勤の流れと内示・内々示
転勤の流れ(スケジュール)
- 内々示(ないないじ):口頭で事前に転勤の話が伝えられる
- 内示(ないじ):正式な「転勤の予定」が通知される
- 辞令交付:実際の転勤が確定する
📌 転勤の時期例:3月に異動の場合 1月中旬に内示 → 2月に準備 → 3月末に引越し
自衛官の転勤は、事前に「内示(ないじ)」や「内々示(ないないじ)」という形で伝えられます。これは引っ越しや家族の準備のために設けられた制度です。
突然転勤と言われても、住まいや家族の手配ができません。そのため、実際の辞令が出る前に、本人に転勤の予定を知らせる「内示」があり、さらに非公式にその前段階として「内々示」が出ることもあります。
たとえば、3月に人事異動がある場合、1月中旬に内示が出され、そこから住居の手配や転校の準備が始まります。内々示はその1〜2週間前に口頭で伝えられることもあります。
転勤に備えて「内示・内々示」があるおかげで、自衛官本人も家族も準備を進めやすくなっています。制度を正しく理解しておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます。
1-3. 転勤がなくなるケースと家族の承諾
転勤の内示が出たあとでも、事情により転勤が取り消しになる場合があります。また、内々示の段階では家族の承諾が重要になることもあります。
急な任務変更や人事再調整によって、内示が撤回されることは稀にあります。また、単身赴任になる場合は家族と別居する必要があるため、本人の意思だけでなく家族の理解が不可欠です。
転勤は命令ですが、家庭事情を考慮する余地もあり、柔軟に対応されることもあります。事前にしっかりと家族と話し合っておくことが大切です。
賃貸情報アパマンショップ
エリア・路線図から簡単検索。敷金礼金0、バストイレ別、オートロックなど
こだわり条件でぴったりのお部屋見つかります
第2章:転勤先・勤務地の決まり方
2-1. 希望勤務地の提出と優先度
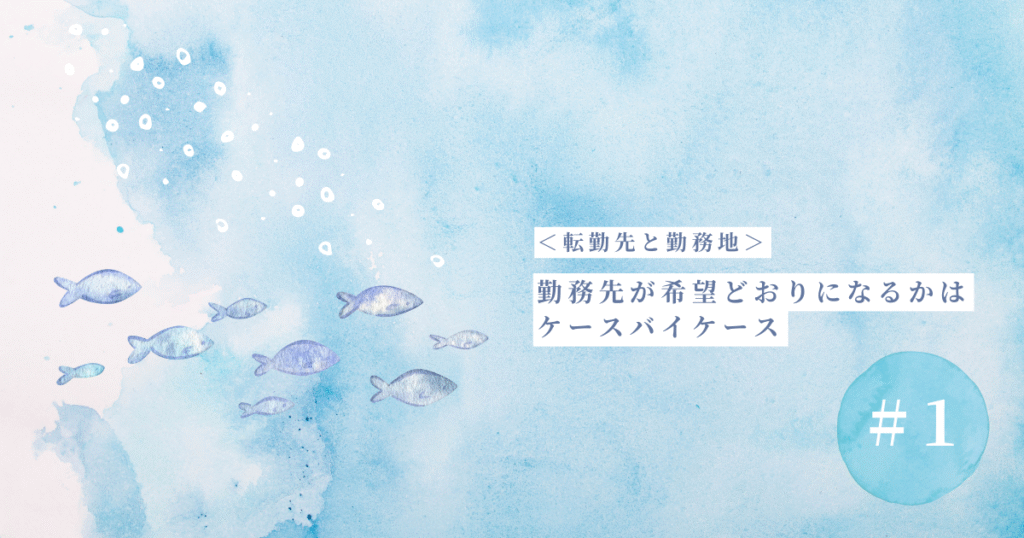
希望勤務地の希望は出せる?
✔ 年に1回程度、「希望勤務地」の提出ができます。
ただし、希望が必ず通るとは限りません。
自衛官は転勤の際に希望勤務地を出すことができますが、それが必ずしも通るとは限りません。
希望勤務地の提出は「人事希望調書」として定期的に提出する仕組みがあります。しかし、実際の配置は部隊の人員バランスや任務の都合によって決まるため、希望どおりになるかはケースバイケースです。
たとえば「子どもの進学に合わせて関東勤務を希望」と書いても、希望者が多い場合や配置可能人数に限りがある場合は、別の勤務地になる可能性があります。
一方で、希望が通ることもあり、特に過去に不利な勤務地を経験している場合は考慮されるケースもあります。

希望は出せますが、あくまで「希望」であって「確約」ではありません!
転勤に柔軟に対応できる心構えを持つことが必要です。
2-2. 勤務地の決定プロセスと考慮事項
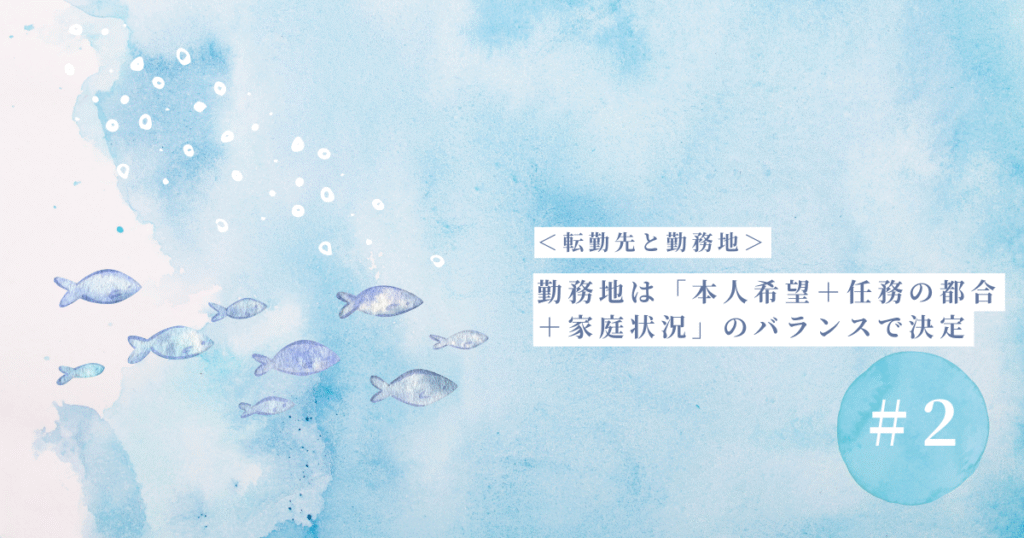
勤務地の決まり方(考慮されるポイント)
| 考慮されること | 内容 |
|---|---|
| 任務の都合 | どこに何人必要か |
| 家族の事情 | 子どもの学校や介護など |
| 持ち家の有無 | 住宅ローン返済中など |
| 階級・職種 | 配置先が限られる場合も |
勤務地は、職種・階級・地域バランス・家庭状況などを踏まえて総合的に決まります。
自衛隊の転勤先決定には様々な要素が絡みます。幹部・曹・士といった階級や、専門職(医官、整備員など)によって配置可能な場所が異なるため、選択肢に制限があります。また、持ち家の有無や育児・介護といった家庭事情もある程度考慮されます。
たとえば、子どもが障害を持っており特別支援学校への通学が必要な家庭では、転勤先を都市部に調整するなど、配慮がされることもあります。一方で、全国どこでも勤務可能とされる若年隊員は、遠方への転勤も多くなりやすいです。
勤務地は「本人希望+任務の都合+家庭状況」のバランスで決定されます。希望が通らなかった場合も、納得できるよう人事制度の仕組みを理解しておくことが大切です。
▼勤務地が決まったら!物件満載のアパマンショップでお部屋探し▼
第3章:転勤にかかる手当・費用支援
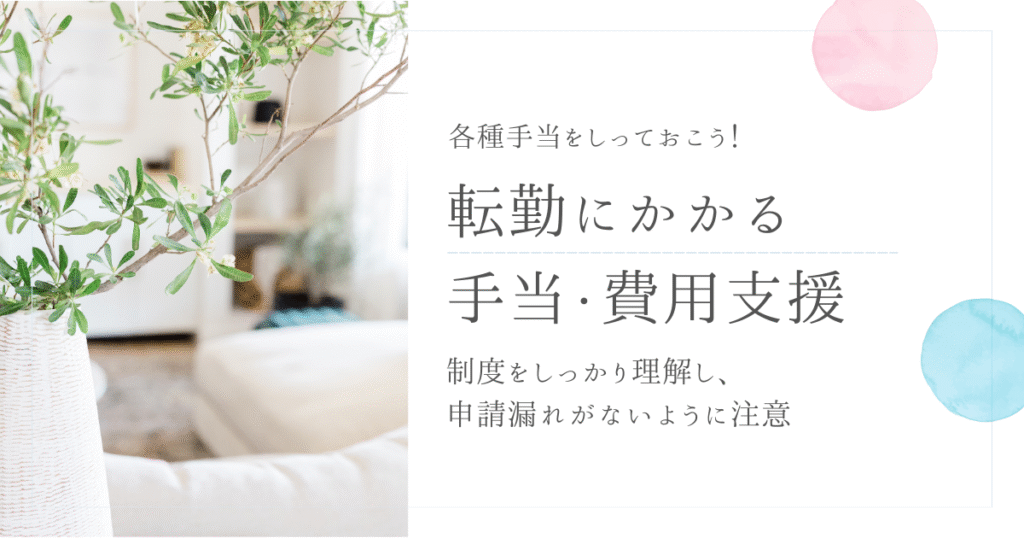
3-1. 支給される主な手当一覧
| 手当名 | 内容 | 支給条件 |
|---|---|---|
| 引越旅費 | 引越し費用をサポート | 家族帯同・単身赴任どちらでもOK |
| 赴任旅費 | 本人や家族の移動費 | 長距離転勤時など |
| 広域異動手当 | 遠距離転勤への加算 | 一定距離を超える場合 |
| 単身赴任手当 | 家族と離れて暮らす自衛官に支給 | 原則60km以上、特例で2km以上(※) |
📌 補足:
「緊急参集要員」に指定されていると、2km以上でも支給対象になります。
転勤に伴って自衛官には複数の手当が支給され、引っ越し費用や移動費が公費でサポートされます。
自衛官の転勤は本人の都合ではなく「命令」であるため、費用負担が生じないよう各種手当が用意されています。代表的なものが「引っ越し手当(引越旅費)」「赴任旅費手当」「広域異動手当」などです。
たとえば、家族を帯同して北海道から九州に転勤する場合、以下のような手当が支給されます:
- 引越旅費:引越業者費用や荷物運搬費
- 赴任旅費手当:本人や家族の移動交通費
- 広域異動手当:異動距離が長い場合に支給される加算手当
転勤による金銭的な負担は国が手当でカバーする仕組みがあります。制度をしっかり理解し、申請漏れがないように注意しましょう。
3-2. 単身赴任手当とは?
「単身赴任手当」は、家族を残して一人で転勤先に赴く自衛官に支給される手当で、生活費の負担軽減が目的です。
家族と別々に暮らす場合、家賃や光熱費が2重でかかるため、それを補うための制度として単身赴任手当が設けられています。原則として勤務地と自宅が直線距離で60km以上離れていることが条件ですが、「緊急参集要員」として登録されている場合は2km以上でも支給対象になります。
単身赴任手当は月額約3〜6万円程度が目安です。たとえば、首都圏で自宅を持っている自衛官が、遠方の駐屯地に1人で赴任した場合、手当で赴任先の家賃の一部をカバーできます。
また、緊急参集要員として指定されている場合、自宅から駐屯地まで2km以上離れていれば手当が出ることがあります。
単身赴任手当は、自衛官の負担を減らし任務に集中できるようにする大切な支援制度です。要件を満たすかを確認し、必要に応じてしっかりと申請しましょう。
第4章:単身赴任先での生活環境
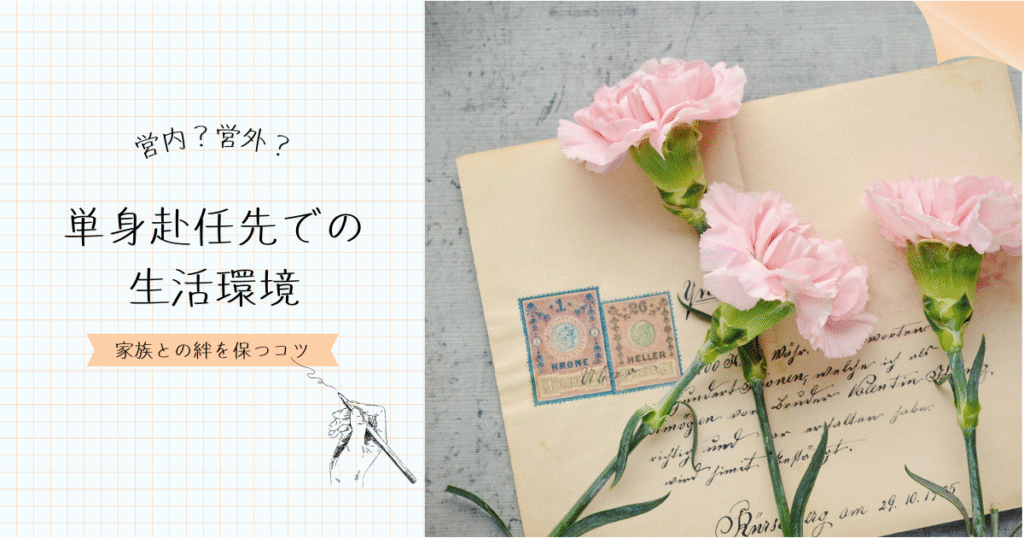
● 営内(えいない)とは?
- 自衛隊の寮のような施設
- 食事や風呂、洗濯機などが完備
- 家賃が安く、食堂でご飯が食べられる
● 営外(えいがい)とは?
- 民間のアパートやマンションでの一人暮らし
- 自炊や掃除も自分で
- 自由度は高いが生活費もかかる
4-1. 営内・営外の違い
自衛官の単身赴任生活は、「営内(えいない)」か「営外(えいがい)」に分かれます。それぞれの生活環境には特徴があります。
営内とは、自衛隊が管理する宿舎(いわゆる寮)のことで、食事や風呂などの生活インフラが整備されています。一方、営外とは、民間のアパートやマンションに住む形で、より一般的な生活スタイルになります。
例えば、若い自衛官や士階級の多くは営内で生活する傾向があります。営内では3食付き、寮費も安価で、通勤時間も短く済みます。
一方で、幹部や家庭を持つ年齢の曹などは、営外に住むことが多く、自分で部屋を借りて食事や生活用品を用意する必要があります。
どちらの生活形態にもメリット・デメリットがありますが、自分のライフスタイルや勤務内容に応じて最適な環境が選ばれます。事前にどのような施設があるか確認しておくと安心です。
4-2. 家族と離れて暮らす上での配慮
● 家族との連携がカギ
- 定期的に連絡をとる(LINE・ビデオ通話など)
- 土日に帰省できるようスケジュールを調整
- 子どもや配偶者の不安もこまめにケア
単身赴任は心身ともに負担がかかるため、家族との連携とコミュニケーションがとても大切です。
自衛官の仕事は規則正しく厳しい一方、家族と離れることで心のケアが難しくなることもあります。特に子育て中の家庭や介護中の家族がいる場合、単身赴任は大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、家族とよく話し合い、お互いに理解と協力が必要です。
たとえば、お子さんがまだ小さい家庭では、週末に帰省する計画を立てる、毎晩テレビ電話をする、など小さな積み重ねが家族の安心感につながります。また、勤務先の上司に事情を相談し、できるだけ帰省の機会を作ってもらうことも可能です。
単身赴任は家族との信頼関係をより大切にする機会でもあります。しっかりと準備をし、定期的な連絡や帰省を通じて、離れていても家族の絆を保ちましょう。
▼北海道から沖縄まで。物件豊富なアパマンショップで新生活のお部屋探し!▼
第5章:実際に単身赴任手当を活用するには

単身赴任手当の申請方法と使い方
● 必要な書類(例)
- 単身赴任届
- 家族の住民票
- 住宅の賃貸契約書
- 勤務地から自宅までの距離証明(Google Mapなど)
📌 申請は人事担当を通して行いましょう。
5-1. 事前準備と申請手続き
単身赴任手当を受け取るには、必要書類の準備と正式な申請手続きが必要です。うっかり申請漏れがないよう注意しましょう。
手当は自動的には支給されず、申請しなければ受け取れません。赴任先での住宅契約や通勤距離の証明、家族の住民票などの提出が求められる場合があります。
実際のケースでは、「単身赴任届」「距離証明書」「扶養家族の住民票」などが求められ、勤務先の人事課を通して申請します。申請後に審査され、翌月または翌々月から手当が支給されるケースが多いです。
手当をしっかり受け取るためには、引越し前後のスケジュール管理と書類準備が重要です。人事担当と早めに相談して、漏れなく申請しましょう。
5-2. 単身赴任手当で生活を安定させる工夫
● 手当の使い道(活用例)
| 活用方法 | メリット |
|---|---|
| 家賃補助 | 二重生活の負担が減る |
| ローン返済 | マイホーム購入の支援に |
| 貯金 | 将来の転勤や退職後の準備に |
| 帰省費用 | 定期的な家族との時間に |
単身赴任手当は、生活費の補填としてだけでなく、住宅ローン返済や貯金にも活用できます。上手に活かせば生活が安定します。
単身赴任手当は月3〜6万円程度支給されるため、これを生活費に充てるのも良いですが、住宅ローンの補助や将来の資金として使う人もいます。特に家族が持ち家に住んでいる場合は、返済の助けになることもあります。
たとえば、地方にマイホームを購入し、本人だけ単身赴任して手当を受け取りながら返済に充てるという活用方法があります。場合によっては、中古住宅を購入して実質的に数百万円分の手当が得られたという事例もあります。
単身赴任手当は、ただの補助金ではなく、家計戦略の一部として考えると大きな力になります。計画的に使い、将来に備えることをおすすめします。
第6章:Q&A・よくある相談例
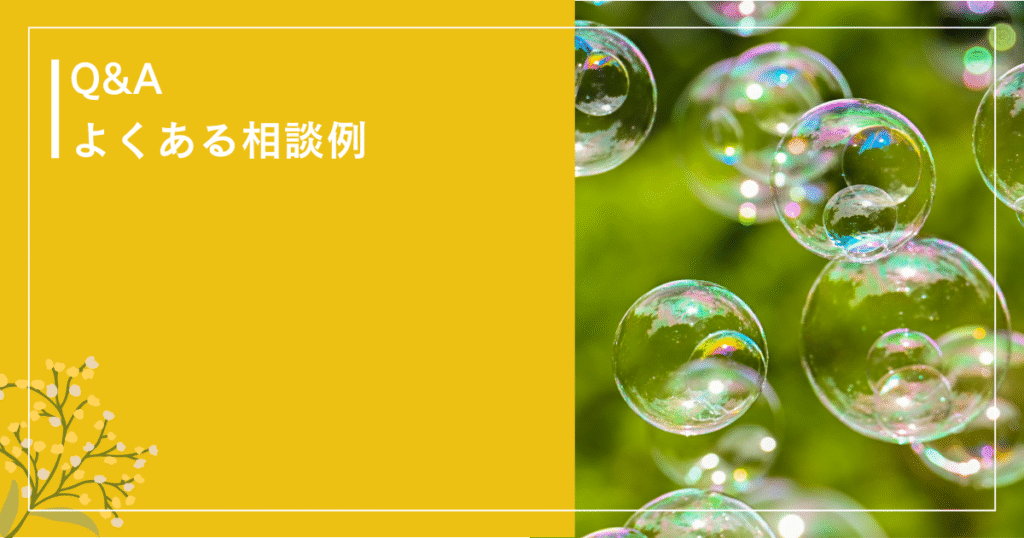
Q1. 家族が転居しても単身赴任手当は出ますか?
家族が転居して一緒に暮らす場合は、単身赴任手当の支給対象から外れます。
単身赴任手当は、「自衛官本人と扶養家族が別居していること」が支給条件です。家族が一緒に引越してきた場合は「単身赴任」ではなく「帯同赴任」扱いになり、手当の対象ではありません。
たとえば、関東に住んでいた家族が、赴任先の九州に転居して一緒に暮らし始めた場合、その時点から単身赴任手当は打ち切られます。ただし、引っ越しに伴って発生する旅費や住居手当など、他の手当は対象になることがあります。
単身赴任手当は「家族と別に暮らすこと」が前提です。状況が変わった場合は、すぐに届け出をして手当の調整を行いましょう。
Q2. 実家の近くに転勤しても手当はもらえるの?
距離と生活実態によっては、実家の近くであっても単身赴任手当が支給されることがあります。
手当の支給条件は「勤務地と家族の住む場所の直線距離が60km以上離れていること(または緊急参集要員は2km以上)」です。そのため、実家に近くても、本人が1人暮らしをしていて家族と別居していれば手当対象になることがあります。
例えば、自衛官の勤務地が新潟市で、実家が長岡市(約80km)にあるケースでは、本人が新潟市内に住み、家族が実家や持ち家に残る形であれば、単身赴任手当の対象になります。
距離と居住実態が重要です。形式的に「別居」していても実態が伴わない場合は不正受給になるため注意しましょう。
Q3. 帰省費用は支給されますか?
単身赴任中の定期的な帰省費用は、原則として手当とは別に支給されません。
単身赴任手当には「生活費の補助」は含まれますが、交通費としての帰省費は基本的に自己負担です。ただし、一部例外(寒冷地勤務、へき地勤務など)では、年に数回分の帰省旅費が支給されることがあります。
たとえば、沖縄の離島勤務など、特に条件が厳しい勤務地においては、年2回程度の航空券相当額が支給される場合があります。詳細は勤務先の人事課で確認が必要です。
通常は自己負担での帰省となりますが、勤務先の地域や配置先の条件によって例外もあります。都度確認しておくことが大切です。
【まとめ】単身赴任手当はもらうべき?
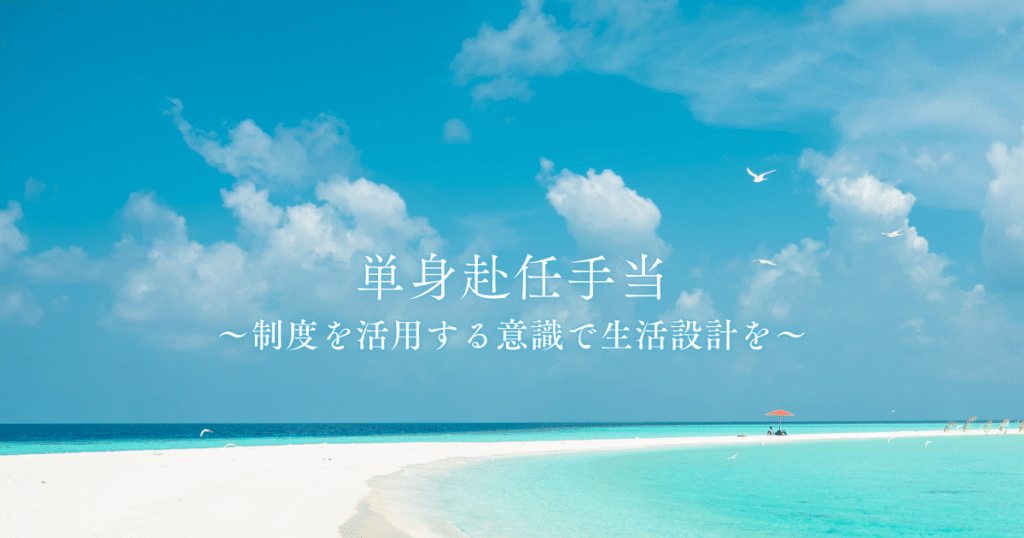
単身赴任手当はしっかり活用すべき
📌 単身赴任手当は、自衛官が「家族と別れて暮らす」ことに対する経済的なサポートです。
✅ 対象になるなら必ず申請しましょう。
✅ 手当は生活費の補助だけでなく、将来への備えにもなります。
✅ しっかり制度を理解して、損をしないように!
自衛官の単身赴任手当は、生活費の補助だけでなく、家族との二重生活を支える重要な制度です。対象になるなら、確実にもらうべきです。
転勤によって発生する金銭的・精神的な負担は、少しでも軽減すべきです。手当を正しく受け取ることで、自分と家族の暮らしの安定に直結します。また、持ち家の購入や家計設計にも活かせるメリットがあります。
たとえば、単身赴任手当を活用して住宅ローンの一部に充てたり、赴任先の家賃にあてたりすることで、無理のない二重生活を実現している自衛官は多数います。工夫次第で貯金にもつながります。
単身赴任手当は、制度を正しく理解し、必要な手続きさえすれば確実に得られる「権利」です。制度に振り回されるのではなく、制度を活用する意識で生活設計をしましょう。
🔗 関連記事もチェック!
▼転勤が決まったけど、官舎には入りたくない人はアパマンショップでお部屋探し!